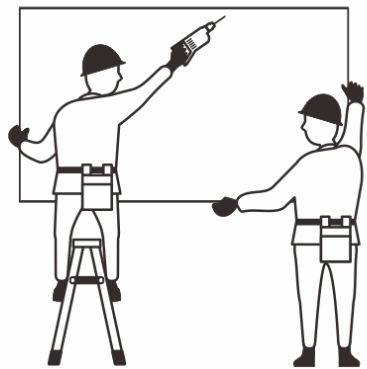建設業許可には29種類の業種があり、ご自身の施工予定の工事が、何の業種に該当するのか判断に悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に上下水道工事を専門とされている方は「管工事」と「水道施設工事」のどちらの業種区分に該当するか、迷われた経験はありませんか?
実はこの2つの区分は、工事内容によって明確に区分されており、間違った選択をしてしまうと建設業法違反となるリスクがあります。
今回はこの二つの業種区分の違いと、判断基準について解説します。
なぜ業種区分が重要なの?
前述した通り、建設業許可は、29の業種に分かれています。請け負う工事が、許可を取得する工事に該当しない場合、その工事は「無許可営業(工事)」とみなされてしまいます。
本来「水道施設工事」に該当する工事にも関わらず、「管工事」の許可のみで工事を行ってしまうと、悪気がなくても無許可営業として行政指導や罰則の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
また、経営事項審査(経審)においても、完成工事高はそれぞれの業種区分ごとに計上しなければなりません。万一、誤った区分で計上すると、経審結果が不正確となり、入札参加資格においても影響を及ぼすこともあります。
「管工事」と「水道施設工事」の定義
まずは、それぞれの業種区分の定義を確認する必要があります。
管工事とは?
管工事は「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属制等の管類を配管する建設工事」を指します。
具体的には以下の工事が該当します。
・給排水、給湯、冷暖房、空調設備の配管工事
・ガス配管工事
・ダクト工事
水道施設工事とは?
水道施設工事は「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を築造する工事」を指します。
具体的には以下の工事が該当します。
・取水塔、浄水場、配水池の築造工事
・公共下水道の処理施設(終末処理場)の築造工事
・上記これらの施設を連絡する導水管、送水管、配水管の布設工事
判断基準は?
具体的にどのような基準で判断すればよろしいのでしょうか?
実務上、特に注意するべきポイントを3つ挙げます。
ポイント1:発注者が誰か?(公共工事の場合)
公共工事の場合、発注者や工事名称が重要な判断基準となります。
地方公共団体の上下水道局や水道事業団体からの発注で、「配水管布設工事」などの名称であれば「水道施設工事」に該当する可能性が高いと言えます。
一方、民間住宅の水道工事や公共施設内の給排水工事であれば、「管工事」となります。
ポイント2:どこからどこまでを工事するの?
工事を行う範囲も重要な判断基準となります。
「水道施設工事」は主に水道事業団体の施設(浄水場、配水池など)や、幹線道路に埋設された配水管など、公的な施設における工事を指します。
「管工事」は、建物の敷地内の給排水管など、主に建物内部や室内における工事を指します。
ポイント3:どちらの許可が必要か?(併用する場合)
上下水道工事を専門とする事業者は、「管工事」と「水道施設工事」の両方の許可を取得しておくことが、非常に有利といえます。それは、地方自治体から発注される公共工事では、両方の許可を求められるケースが少なくないからです。
具体的には、新しい団地の造成工事で、配水管を敷設し、その後各戸に引き込む給水管を設置する工事の場合、配水管の敷設は水道施設工事となり、各戸に引き込む給水管は管工事となるからです。
「管工事」と「水道施設工事」の区分は、複雑でややこしくみえますが、「公共的な施設・幹線」か「建物・敷地内」かという視点で考えると、分かりやすくなります。
・公共インフラとしての上下水道工事→水道施設工事業
・建築物の設備としての配管工事→管工事業
ただし、境界線があいまいなケースも多いため、個別の工事内容に応じて判断する必要があり、迷われた場合は、事前に管轄の許可行政庁へ確認することが重要です。
当事務所では建設業許可申請はもちろん、業種判断についてもサポートさせて頂きます。
お気軽にご連絡下さい。