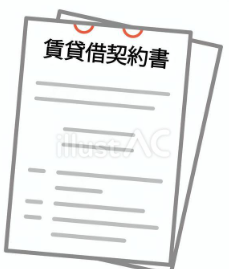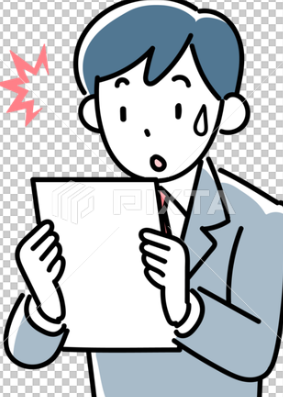会社の事務所や資材置き場の賃貸借契約を結ぶ際、貸主が会社の代表者ご自身である場合、注意しなければならないポイントがあります。
今回は貸主が代表者個人で、借主が自社(法人)となる賃貸借契約において、気を付けるべきポイントについて解説します。
ポイント1:契約が客観的で明確な取引であること
「身内だから契約書なんてなくても大丈夫だろう..」と考えてる方もいらっしゃいますが、契約書は必要です。たとえ貸主と借主が身内関係にあっても、代表者個人と代表者が経営する法人は法律上、別人格です。
契約書がないことによって、契約内容が不明確となり、第三者から不透明な取引だと信用問題になります。
また、税務調査で賃料の妥当性を疑われるリスクもあります。必ず契約書を締結し、証明できるようにしましょう。
ポイント2:契約書の記載事項でチェックすべき点
一般的な賃貸借契約書に加えて、以下の項目は特に注意する必要があります。
①賃料の妥当性
賃料は、近隣の相場や物件の広さ、築年数、設備などを考慮して客観的にみて妥当な賃料を設定する必要があります。例えば相場よりも著しく高額な場合、不当な経費とみなされ、損金算入が認められない可能性があります。また、逆に低すぎる場合も不当に利益を許与しているとみなされるリスクもあるのです。税務上の相談は事前に税理士に相談したり、近隣相場を調べるなどして妥当性を裏付ける資料を準備しておくことが望ましいです。
②契約期間と更新条項
契約期間を明確に定める必要があります。その他、自動更新か更新契約書の取り交わしの有無や更新料の有無なども明記します。
③敷金・保証金
敷金や保証金の額、返還条件、原状回復費用など、具体的に記載します。特に、代表者個人から会社へ金銭を預ける形になるため、将来的に返還が必要となった際のトラブルを未然に防ぐためにも、細部まで定めておくことが望ましいです。
④用途の制限
建物の一般的な契約でいえば、居住用賃貸借契約が挙げられますが、建設業許可要件としては契約書が事業用賃貸借契約もしくは「事務所として使用する」旨の文言を契約書に明記しなければなりません。居住用としては認められませんので注意が必要です。また、事務所の利用以外に、資材置き場や駐車場として使用する場合は、その旨を明記しておきましょう。これは後から用途違反を指摘される可能性があるためです。
⑤修繕義務の負担
貸主、借主の修繕義務の範囲を定めておくことが必要です。例えば大規模な修繕(屋上防水工事など)は貸主負担、日常的な小規模な修繕(消耗品の交換など)は借主負担といったように、範囲を定めます。
ポイント3税務上の注意点
※ポイント3については一般的な情報提供の範囲にとどまっています。税務に関する個別具体的な計算や申告書の作成、個別の税務相談につきましては税理士へご相談して頂く必要があります。
貸主、借主が身内である場合、税務署から厳しくチェックされる可能性があります。
①貸主である代表者が個人の場合 消費税の納税義務者ではないケースが多いです。そのため、賃料に消費税を含めるがどうかは、明確にしておく必要があります。一般的な個人間の不動産賃貸取引は非課税となりますが、事業として行っていると見なされれば課税対象となるため注意が必要です。
②源泉徴収
代表者が会社から賃料を受け取る場合、賃料は不動産所得となります。不動産所得に対しては、原則として源泉徴収は不要なのですが、その事務所に会社の従業員が常駐して、管理業務を行っている場合は、「不動産の貸付」ではなく、「管理業務等の役務提供」と見なすことがあります。この場合は、賃料は給与所得として会社が源泉徴収義務を負う可能性があります。
ポイント4:会社法上の注意点
会社法では身内同士の取引は「利益相反取引」と疑われる可能性があります。
利益相反取引とは、会社と代表者の利益が相反する取引のことで、会社に不利益をもたらす可能性がある取引のことをいいます。その場合は、取締役会の承認または株主総会の承認が必要になります。契約が無効とならない様に、手続きを怠らないようにしましょう。
上記、注意すべきポイントをおさえて、適切に手続きを行えば、基本、何ら問題はありません。しかし「身内だから..」と契約内容を不明確なままにしておくと、後々のトラブル、税務上の問題が生じるリスクがあります。
当事務所では建設業許可申請はもちろん、賃貸借契約書の作成やご相談を承ります。建設業許可のご依頼を頂いたお客様には、賃貸借契約書を無料で作成いたします。また当事務所へ建設業許可のご依頼を頂ければ、提携先の税理士へのご紹介も行います。お気軽にご相談ください。