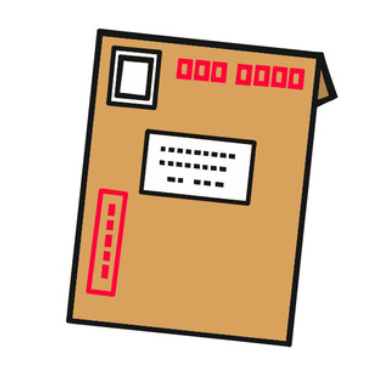2024年12月の建設業法改正により、従来の「専任技術者」と呼ばれていた技術者が「営業所技術者」と名称変更されました。それに加えて現場技術者との兼任に関する要件が大幅に緩和されました。 この改正は建設業許可にとって大きな改正といっていいでしょう。 今回は現場技術者、営業所技術者等の兼任をテーマに要件を解説します。
制度変更の概要
(1)名称変更「専任技術者」から「営業所技術者」へ
この変更は単なる名称変更ではなく、営業所単位での技術管理体制の明確化という重要な意味を持ちます。
一般建設業者の場合は「営業所技術者」と呼び、特定建設業者の場合は「特定営業所技術者」と呼びます。
(2)現場技術者の兼任制度の新設
今回の改正では、主任技術者・監理技術者の工事現場兼任制度が新設されました。これを専任特例1号と呼びます。これにより、一定の要件を満たす場合に、同一の技術者が最大2つの工事現場を兼任することが可能となりました。
(3)営業所技術者の現場兼務制度
この制度によって、専任を要する工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務することが可能になりました。
ただし、営業所技術者は兼務できる現場は1つに限定されています。
現場技術者兼任の要件(専任特例1号)
現場技術者が複数の工事現場を兼任するためには、以下の8つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:建設工事の請負代金の上限
兼任する各建設工事の請負代金が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)である必要があります。
万一、工事途中で請負代金額がこの上限を超えた場合は、それ以降は専任の配置が必要ですのご注意ください。
要件2:兼任できる工事現場数
同一の主任技術者または監理技術者が兼任できる工事現場は2つまでとなります。 専任を要しない工事現場との兼務は可能ですが、全体の工事現場数が2を超えてはなりません。
要件3:下請次数の制限
下請契約の次数は3次までに限定されています。工事途中で下請次数が3を超えた場合は、専任配置が必要になります。
要件4:連絡員の配置
各工事現場に、主任技術者または監理技術者との連絡、その他必要な措置を講ずるための連絡員を配置する必要があります。また、土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該工事に関する実務経験を1年以上有する者に限定されます。
要件5:工事現場間の距離
兼任する工事現場間の距離は、技術者が1日の勤務時間内に巡回可能で、かつ移動時間が概ね2時間以内(片道)である必要があります。
要件6:人員配置計画の作成・保管
技術者の配置を示す詳細な計画書を作成し、工事現場に備え置くとともに、営業所でも保存する必要があります。
要件7:施工体制確認のための情報通信技術
現場作業員の入退場を遠隔から確認できる情報通信技術の措置を講じる必要があります。 CCUS(建設キャリアアップシステム)またはCCUSとAPI連携したシステムの使用が望ましいとされています。
要件8:現場現状確認のための情報通信機器
技術者が他の工事現場から現場状況を確認するため、映像と音声の送受信が可能な情報通信機器を設置し、通信環境を確保する必要があります。
営業所技術者の現場兼務要件
営業所技術者が専任を要する工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務する場合の要件は、基本的に専任特例1号と同様ですが、いくつか異なる点があります。
・工事契約の要件:営業所技術者が所属する営業所において、請負契約が締結された工事であること
・兼務現場数:1工事現場まで
・距離要件:営業所から工事現場までの移動時間が概ね2時間以内であること
・雇用関係:営業所技術者は、該当請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
既存制度との関係
営業所に近接し、専任を要さない工事現場の主任技術者等の兼務は引き続き可能です。 また、営業所に近接していない専任を要しない工事現場についても、専任現場の兼任要件をすべて満たせば兼務が可能となりました。
〈注意点とポイント〉
ポイント1:標識の記載方法
専任特例1号を適用している場合は、工事現場の標識の「専任の有無」欄に「非専任(情報通信技術利用)」と記載する必要があります。
ポイント2:制度の併用制限
営業所技術者等が専任現場の職務を兼務する場合、現場技術者の兼務との併用はできません。
ポイント3:情報通信機器の要件
一般的なスマートフォンやタブレット端末、ウェブ会議システムでも、映像・音声の送受信が可能であれば要件を満たします。ただし、山間部など通信環境が不十分な地域では、要件が満たさない場合があります。
ポイント4:連絡員の役割
連絡員は専任や常駐は求められませんが、技術者が遠隔から指示する際の現場側での適切な伝達や、事故等への対応など、円滑な施工管理の補助を担います。
制度活用のメリット
人材の効率的活用
限られた有資格者を複数の現場で活用することで、人材不足の解消と工事の円滑な進行が期待されています。
コスト削減
技術者を複数の現場で分散できるため、人件費や工事原価の削減につながります。
技術者のキャリア形成
複数の現場を経験することで、技術者のスキル向上とキャリア形成を促進できます。
この改正により、人手不足の解消と効率的な工事施工を実現できる一方、詳細な要件を正しく理解し、適切な管理体制を構築することが不可欠です。
お問い合わせはこちら↓