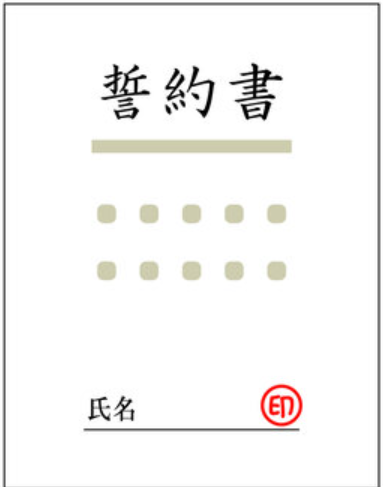建設業を営む中で、許可取得を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その際に、「費用がいくらかかるのか?」気になる方も多いのではないでしょうか?
今回は、新規取得から更新、業種追加、そして最新の電子申請まで、かかる費用を具体的な手数料を交えて解説します。
(1)建設業許可申請に要する「法定手数料」
この手数料は、国や都道府県に支払うもので、法定手数料となります。
新規申請
・大臣知事(一般・特定) 9万円
・大臣知事(一般・特定) 15万円
なお、一般と特定では法定手数料の違いはありません。
業種追加
・知事免許(既存許可への業種追加) 5万円
・大臣免許(既存許可への業種追加) 5万円
既に許可を持っていて、さらに別の業種を追加する場合の費用です。
更新
・知事免許(5年毎) 5万円
・大臣免許(5年毎) 5万円
5年間の有効期間が、満了する約3ヶ月前から申請が必要です。
その他の変更等
・般特新規(一般許可から特定許可への切り換えなど) 10万円
・廃業届、役員変更届、決算変更届など 手数料は原則不要(ただし、申請内容によっては別途手数料が発生する場合があります。)
(2)手数料の支払い方法は?
原則、収入証紙(都道府県)または収入印紙(国)による納付
電子申請の場合は、クレジットカードやPay-easyなどのキャッシュレス納付が主流になりつつあります。
電子申請は、令和5年1月より始まった「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による申請によるのもので、従来の証紙、印紙から、キャッシュレス決済に移行している流れとなっています。電子申請の導入により、行政庁への出向く時間や証紙、印紙の購入が不要になるなどのメリットがあります。
ただし、電子申請のシステムを利用するには、GビズIDなどの準備が必要です。また、すべての都道府県で完全に移行しているわけではありませんので、各々の管轄許可行政庁のホームページ等で確認する必要があります。
(3)行政書士への依頼費用は?
法定手数料とは別に、専門家である行政書士に手続きを依頼する場合にかかる費用になります。各行政書士事務所によって、報酬額は異なっていますが、今回は当事務所のケースで記載します。
行政書士に依頼するメリット
煩雑な書類作成や添付書類の収集、経営管理体制の確認などの手間が削減でき、本業に専念して頂けるようサポート致します。また、法令遵守(コンプライアンス)の観点から専門家の視点で、注意事項を支援します。
報酬額
当事務所料金
※当事務所料金につきましては、当事務所の方針や経済情勢などにより変動する場合があります。
まとめ
建設業許可の申請費用には、「法定手数料」と「行政書士報酬」の合算額が、主にかかる費用といえます。これらの費用はかかりますが、これにより請負金額500万円以上の工事が可能となり、大きな工事を受任することができます。
当事務所では建設業許可申請を承っています。お気軽にご相談ください。