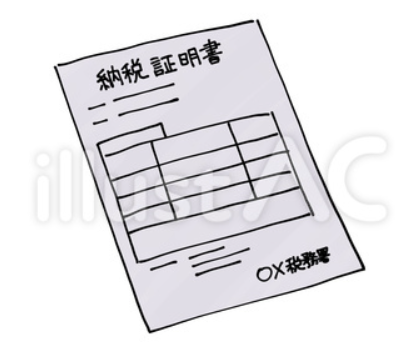建設業を営む事業者の方々で、事業承継を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?将来の世代や後継者へスムーズに引き継ぐ「事業承継」は、建設業界の持続的な発展にとって、避けては通れない重要な経営課題といえます。
令和2年10月の建設業法改正前は、建設業許可は、事業承継の際に許可を引き継ぐことができず、後継者が新規で許可を取り直す必要がありました。
新しい許可が下りるまでの間、軽微な工事しか請け負えない許可の空白期間が生じ、経営上の大きなネックとなっていました。
しかし、前述の建設業法改正により、許可承継制度が導入されました。この制度を正しく活用できれば、許可の空白期間を発生させることなく、建設業許可を承継できるようになります。今回は、この承継制度のメリットと、事業承継・相続、それぞれの注意点について解説します。
(1) 承継認可制度の最大のメリット
許可の空白期間がゼロ
建設業許可の承継認可制度で、最大のメリットといえるのが、空白期間が発生しないことではないでしょうか?
これにより、譲渡や合併等の効力発生日、または被相続人の死亡日以降も、承継人は継続して建設業を営むことができます。また、継続して大規模な公共工事や、民間工事の請負契約を締結することができます。
経営事項審査(経審)においても、被承継者が受けていた経審の結果や、完成工事高などの評価も引き継ぐことができるため、改めて一から経審の実績を積み上げる必要がありません。
(2)承継認可のタイムスケジュールと注意点
事業譲渡や合併、分割などによる承継の場合、最も重要なのはスケジュール管理といえます。
事前認可が必須
相続と異なり、事業承継の場合、承継の事実(譲渡・合併)が発生する前に、許可行政庁から認可を受ける必要があります。
準備と申請の目安
スムーズな認可のためには、承継予定日の約3ヶ月~半年前から、準備を始めるのが肝要です。特に合併や分割を伴う場合は、株主総会や取締役会での決定など、会社法上の手続きを並行して進める必要があります。
事前相談
まずは、管轄の許可行政庁の窓口で、事前相談を行います。この事前相談は個々により、日数は異なりますが、承継予定日の数ヶ月前には行うようにしましょう。
申請書類の作成・提出
承継予定日の30日前(許可行政庁によっては、90日前などの場合もあります)までには、申請を完了しておく必要があります。
承継元の許可期間に注意
承継元の許可の有効期間が短い場合、承継後すぐに、更新手続きが必要になる場合があります。残存期間が十分あるか、事前に確認することが重要です。
(3)相続における承継認可の申請期限と注意点
個人事業主の許可承継において、相続は時間的な制約が厳しいです。
これは、個人事業主である被相続人が亡くなった場合、許可を引き継ぐ相続人は、被相続人の死亡後、30日以内に承継認可の申請を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、認可を受けることができず、許可は失効してしまいますので、注意が必要です。
(4)地位の承継の効果
相続により認可された場合、その効力は被相続人が死亡した日に遡って生じます。これにより、死亡日から認可日までの間も、許可を受けた状態とみなされ、許可の空白期間が生じないということです。
(5)相続人が満たすべき要件
相続人が許可を承継するには、被承継者と同様に、以下の要件を死亡時点から継続して、満たしている必要があります。
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件
2.専任技術者の要件
3.財産的基礎の要件
4.欠格要件に該当しないこと
特に、相続人が建設業の経営経験が浅い場合や、専任技術者が新たに必要になる場合は、30日以内の申請期限のなかで要件を整えるのは、非常に困難といえます。
(6)まとめ
このように、承継認可の申請は、通常の新規許可申請以上に、複雑で専門的な知識が必要といえます。
事業承継では、会社法上の手続きや連携、膨大な契約関連書類の準備など、行うべきことが非常に多いです。相続では30日以内と限られた期限のなかで、要件証明を漏れなく行う必要があります。
当事務所では皆様の事業が途切れることなく、継続できるよう適切な手続きと、速やかな対応でサポートさせて頂きます。まずはご相談下さい。